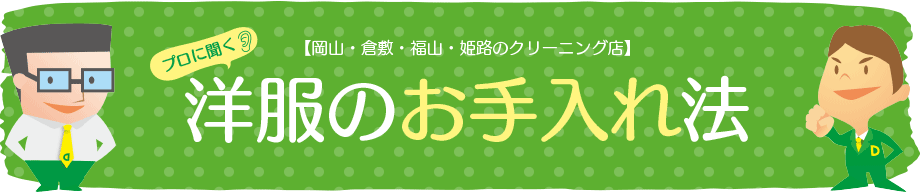柔軟剤の効果はふっくら仕上げるだけではありません。
柔軟剤は、界面活性剤が繊維の表面に膜を作ることで、静電気を抑えて毛羽立ちや毛玉ができるのを防ぎます。
さらにホコリをつきにくくして黒ずみを防ぐ効果もあるんです。
柔軟剤もいろんな種類がありますが、性能に大きな差はありません。
香りの好みで選ぶのがいいでしょう。
柔軟剤を使うときの注意点は、洗剤と一緒に入れないこと!
一緒に入れる人は少ないと思いますが、洗剤と柔軟剤を一緒に入れるとお互いの働きを邪魔してしまいます。
すすぎが終わったタイミングで入れるようにしましょう。
漂白剤のタイプ
なかなか落ちないガンコな汚れには漂白剤を使うことありますよね。
漂白剤は大きく分けて「酸化型」と「還元型」に分かれます。
酸化型は「酸素系」と「塩素系」に分かれます。
洗濯のときに使われるのは酸素系漂白剤がほとんどです。
塩素系のほうが漂白力は上ですが、繊維に与えるダメージは大きいです。
酸素系漂白剤には、液体タイプ(弱酸性)と粉末タイプ(弱アルカリ性)があります。
色柄物には弱酸性の液体タイプを使い、色落ちをそれほど気にしなくてもよいなら弱アルカリ性の粉末タイプを使うとよいでしょう。
白物で汚れがひどいものは塩素系漂白剤を試してみてもいいでしょう。
漂白剤を使うときの注意点は「混ぜるな危険」というやつです。
酸素系漂白剤と塩素系漂白剤を混ぜると塩素ガスが発生します。
塩素ガスは刺激性のある黄緑色の気体。
空気より重いので、発生すると低いところに流れます。
低濃度でも鼻やのど、目に刺激を感じ、吸入すると肺水腫を起こす可能性があります。
許容濃度を超えると死に至ることもある危険なガスです。
これは本当に気をつけたほうがいいですね。
関連記事

セーターやニット製品は着ているうちに毛がへたってきて、風合いがなくなってきてしまいます。
そんなときはクリーニングに出せば、ふっくらさも戻ります。
ふっくらして繊維が空気を含むと、温かさがまったく変わってきます。
高級獣毛である、アンゴラやモヘアなどは特にクリーニングすることで風合い、温かさの違いがよくわかります。
今日はまだクリーニングに出すほどでもないけど、ちょっとへたってきたかな?というときの簡単お手入れ法を紹介します。
セーターなどニット製品は着用後は、けばが乱れています。
ブラシで毛並みを整え、ほこりを取りましょう。
テーブルなど平らな場所に置いて、上の方から軽くブラシをかけていきます。
柔らかい毛を使ったブラシがいいですね。
そしてアイロンでスチームします。
アイロンが直接あたらないギリギリのところで、アイロンのスチームを当てます。
アイロンの蒸気で毛が起き上がって、ふっくらした風合いが戻ってきますよ。
でも、一番いいお手入れは、汚れや臭いが気になるようになる前にクリーニングに出すことです。
関連記事

石鹸の工業化のカギとなったアルカリ剤。
アルカリは油汚れ、タンパク質汚れを落とす働きがあり、アルカリ助剤を配合した石鹸が多いんですね。
ところで、このアルカリ成分は野菜のあく抜きにも使われます。
山菜をゆがくときにワラ灰を入れるとよいという話、聞いたことありませんか?
野菜の苦味やエグ味、シブ味、切り口が黒くなったりする「アク」には、シュウ酸やアルカロイド、タンニンといった体に害を及ぼす成分が含まれています。
ほとんどの植物の葉、茎、根には昆虫や外敵より身を守るためにアクを持っているんですね。
なので調理前に取り除く必要があるのですが、そのときに効果を発揮するのがアルカリ成分。
灰に含まれる炭酸カリウム、炭酸ナトリウムなどのアルカリ成分がアクを取り除いて、調理に適した状態にしてくれるんですね。
関連記事

家庭用洗濯機の進化はすごいですね。
ついに温水洗いができる全自動洗濯機が登場しました。
価格的にはまだまだ高いし、洗濯にかかる時間が長いので、このまま普及するのは難しいかもしれませんが、家庭で簡単に温水洗いができる時代がもうすぐ来るのかもしれません。
さて、今日はさまざまある洗濯機を選ぶときのポイントと使い方のコツをお伝えします。
今、家庭用洗濯機の主流は縦型とドラム式です。まだ縦型のほうが多いみたいですね。
縦型洗濯機は、たっぷりの水で洗うため汚れが水に溶けやすいので、汚れものを大量に洗うときに向いています。
一方ドラム式は、ドラムの回転により衣類を落下させてたたきつけることで汚れを落とす方式です。
少ない水量で洗えるのが特徴です。
ヨーロッパではドラム式が普及していますが、これはヨーロッパでは水道水に硬水が多く、洗剤が溶けにくいという事情によるものです。
ドラム式は少ない水で洗うので衣類のごわつきが気になるという人もいるようです。
洗濯機を選ぶときのポイントは、家庭のスタイルによります。洗濯の頻度、量、汚れの種類などを考えて、自分の家庭にあったものを選びましょう。
お子様の部活などで汚れのひどいものが多いというご家庭では縦型がいいでしょうし、子供も成人して夫婦2人だけというご家庭ならドラム式がいいでしょう。
洗濯機を上手に使うコツ
洗濯機は機種によって容量がさまざまです。
上手に洗濯をするコツは容量の8割程度に抑えること。
例えば7kgの洗濯機であれば、6kg弱でまわすようにする。
詰め込みすぎると、十分な洗浄ができません。
ただ、洗濯物の量が少なすぎても摩擦効果が出にくいので、少なくとも容量お6割くらいは入れてまわすようにしましょう。
水量で考えるなら、縦型洗濯機の場合、理想は水量の1割程度の洗濯物です。
50リットルの水で洗うなら、洗濯物は5kg程度。
衣類の重さを体重計で量るようにして、だいたいの感覚をつかむと洗濯レベルがあがりますね。
関連記事

今年は暖冬と言われていますが、それでもコートを着る機会もあると思います。
今日は、水洗いできないウールのコートのお手入れ法をお伝えします。
水洗いできない衣類もちょっと手をかけるだけで長持ちしますよ。
ウールのコートやスーツは脱いだらハンガーにかけ、こまめにブラッシングをしましょう。
表面が汚れてくるのはホコリが原因です。
こまめにホコリを落とすことでキレイに着ることができます。
首まわりや袖口は汚れが目立たないうちに「たたき拭き」をしておきましょう。
ウール製品は水洗いできませんし、水気が残るとシミになります。
水で濡らして固く絞った布で、パンパンとたたく感じでふき取ります。
水分が衣類に残らないように、しっかり乾かしながらふき取ります。
最後に、アイロンのスチームを当てておくと、シワが伸びてふっくらするとともに、タバコの臭いなどを消すこともできます。
ただ、シーズンが終わって衣替えをするときは、必ずクリーニングに出してくださいね。
そのまましまうと、シミや臭いが発生してしまうことも。
クリーニングに出して、見えない汚れまでしっかり落としてしまいましょう。
関連記事