
ファッション
DIA blog

ファッション

ファッション

ファッション

ファッション

ファッション

ファッション
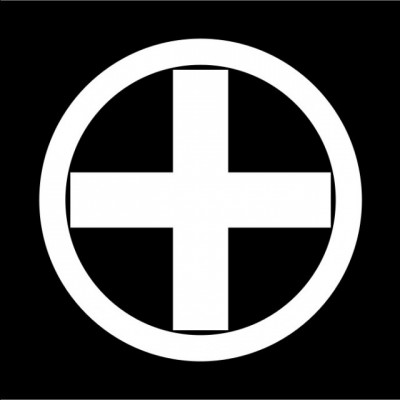
ファッション

ファッション

ファッション

ファッション

ファッション

防虫剤の正しい使い方